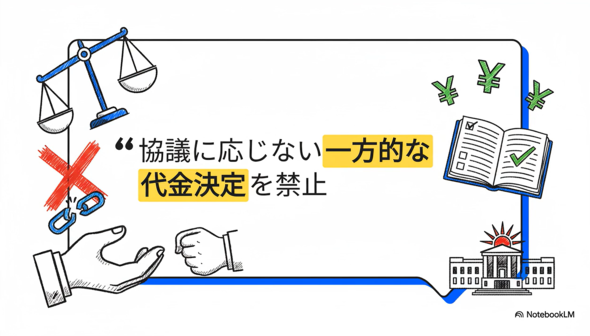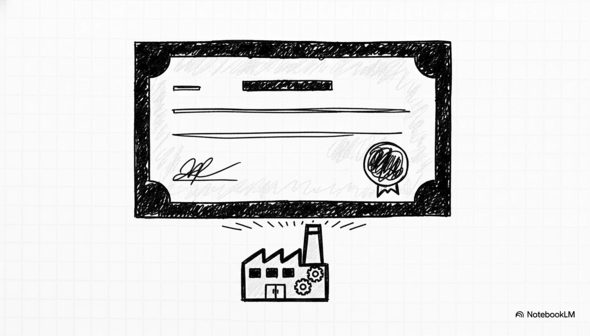【総務・情シス向け】社内レクチャー用資料をNotebookLM「Studio」機能で自動製作:NotebookLM使いこなし
NotebookLMは基本のチャット機能だけでも自身の理解促進や社内用チャットbot作成に使える。「Studio」機能群を使えば、社内の情報共有用コンテンツ制作にも活用できる。
「Google Workspace」に含まれる生成AIツール「NotbeookLM」は、資料を読み込ませればそれをもとにユーザーの質問に応答できる専門チャットbotを作れます。社内のルールを登録してメンバーに公開すれば社内問い合わせbotにもでき、ビジネスでの活用がしやすい生成AIの一つです。
そんなNotebookLMには「Studio」という機能群があります。これは登録された資料を基にさまざまなコンテンツを生成するものです。事業部門の従業員が業務上の資料を読み込ませて、自分の内容理解促進に使うのもいいですが、情報システム部や総務部などのバックオフィス部門が社内向けの資料を作るのにも便利です。
今回はこのStudioを使って、1つの資料からさまざまな社内用の情報共有コンテンツを作ってみます。題材として、「下請代金支払遅延等防止法」(下請法)から名称が変更され2026年1月1日に施行される「中小受託取引適正化法」(取適法)を使います。
資料を基に動画やクイズを作れる
NotebookLMは生成AIチャットツールの一種です。「ChatGPT」や「Copilot」のようにユーザーの質問に対して生成AIがテキストで応答しますが、その際にユーザーが登録した資料を参照するのが特徴です。社内規定やガイドライン、設備の使い方マニュアルなどを登録しておけば、「自社のルールに詳しい生成AIチャットbot」を作れるため、これを使って社内ヘルプデスク業務の一部を代替させることもできます。
Studioは、資料を基に「音声解説」「動画解説」「マインドマップ」「レポート」「フラッシュカード」「テスト」といったコンテンツを生成できる機能です。
例えば、新しいバックオフィス系SaaSを導入したときの使い方レクチャーや、社内で下請法改正の注意事項についてレクチャーを実施する場合を考えます。社内メールや掲示板で「新ツールの基本的な操作」「下請法改正で知っておくべきこと」のような資料を掲出したり、レクチャー動画を視聴するよう義務付けたり、理解度チェックテストを実施したりと、社内での周知にはさまざまな方法がありますよね。特に下請法改正はかなりの従業員が日常の業務で直接関係する内容ですから、法令順守のためには周知の徹底が重要です。
今回は公正取引委員会が公開している資料「2026年1月から『下請法』は『取適法』へ!」を基にコンテンツを作らせました。なお、生成AI製のコンテンツを外部向けに展開するのはリスクの検討も必要です。基本的には個人利用もしくは社内利用で使うのがいいでしょう。また、コンテンツの内容の正確性は、人間側の責任として都度確認してください。
口語のラジオを作れるが、ダイナミック過ぎるかも?
「音声解説」は資料を基に男女2人が掛け合うニュースラジオ番組を生成できる機能です。資料にある内容だけを正確に音声化するのではなく、2人のラジオパーソナリティーが口語で話し合うような形にアレンジされています。
アレンジの段階で若干ダイナミックな言い方になるのが少し気になります。少なくとも資料に基づいて生成しているコンテンツなので事実が誇張されることはありません。取適法には「遅延利息を支払う義務」という内容があり、遅延利息は年率14.6%に設定されていますが、これを勝手に146%に変えたりはしません。
しかし直後に「これほとんど消費者金融並みの金利じゃないですか」と生成されています。これはニュース記事なら絶対に書かない内容です。この金利をどう評価するかは読者にゆだねられるものであり、少なくとも筆者が記事にするなら高いとも低いとも書かず、14.6%という事実のみを記述します。
社内レクチャーは報道ではないので、主観が混じってもいい面はあります。従業員から必要なだけの注意を引き出すために「14.6%ってかなり高いですよね。だから絶対に遅延しないようにしましょう」のように言うことはあるかもしれません。出来上がったスクリプトは必ず人間が確認し、不要なバイアスを生まないように注意しましょう。
かなりリッチな画面作り 動画は工数をかなり削減できる
動画解説は実質的にプレゼン資料生成のような機能です。こちらは資料を基に「Microsoft PowerPoint」で作ったようなスライドが生成され、そこに口語の音声が組み合わされた動画が出力されます。
プレゼンテーションのスライドは使う人の方針によって仕上がりはさまざまです。見れば全て分かるものを作る人もいれば、トークがメインでスライドはそれを補足するビジュアルを見せるものと割り切っている人もいますが、NotebookLMは後者です。多くの情報は音声にあり、20ページ程生成されたスライドは文字のない画像だけのページもあります。
見た目はかなりいいですね。画像素材を探して、デザインを考えながら配置して、文字にハイライトをつけてといった作業なしにワンクリックでおしゃれな資料ができます。内容を考えて画面を作る作業は時間がかかりますから、この作業を生成AIアウトソースすればかなりの時間削減になりそうです。
ただし、こちらも音声解説と同様、語り口がダイナミックになるので注意が必要です。
程よい理解度クイズ
社内レクチャーでは資料を見た後に理解度テストを実施して、知識の定着を図ることがあると思います。NotebookLMでもクイズを作れます。形式は4択クイズで、難易度も高すぎず低すぎずな印象です。テスト終了時にはスコアも表示されます。受験のたびに内容が変わったりシャッフルされたりすることはありません。
正解不正解にかかわらず、選んだ選択肢には短い解説が表示されます。
4択クイズを作るときには、程よい「はずれ」の選択肢を考えるのが大変です。これを自動でやってくれるのは便利ですね。ただし、従業員の受験状況とスコアを把握するまでがテストですから、NotebookLMで作ったクイズを「Google フォーム」に移植して一元管理できるようにしたほうがいいでしょう。これが連携できると嬉しいですね。
自分で作ったほうがいい レポート、フラッシュカード、マインドマップ
Studioはこの他にもレポート、フラッシュカード、マインドマップも作成できます。レポートは「概要説明資料」「学習ガイド」「ブログ投稿」「研修資料」など複数の形式が選択できます。フラッシュカードは受験などで使われる英単語帳のような暗記カードですね。
ただ、これらは生成AIに頼らず自分で作った方が効果的だと筆者は感じました。勉強のためにフラッシュカードが欲しいなら、フラッシュカードを自分で作るほうが勉強になりますし、思考整理のために作るマインドマップをアウトソースしたらあまり思考整理できませんよね。
レポートは会議の事前準備として使えはしますが、結局基となる資料を読んで理解しないことには人間がレポートを読み上げるだけになります。ただの読み上げなら機械でもできます。
そもそもブログ記事や研修資料はStudioで作らなくてもチャットでできますし、NotebookLMのページを社内で共有したほうが受け取る側の理解を促進できそうです。
NotebookLMは基本のチャット機能だけでも理解促進や社内用チャットbot作成に使える他、本稿で見たように社内の情報共有用コンテンツ制作にも便利です。総務・情シス部門の方々が業務効率化に活用しない手はありません。
この他にも、製造部門が営業部門向けに製品の解説コンテンツを作ったり、上層部が会社のビジョンを周知するための資料を作ったりと、部門を横断して何かを伝えたいときに上手に使えそうです。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.