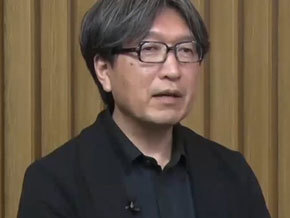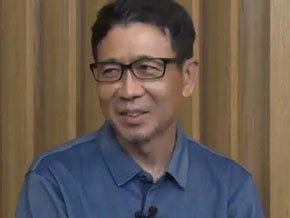RPAの先を行く「ハイパーオートメーション」 現状と課題を議論
RPA(Robotic Process Automation)を他のテクノロジーと組み合わせ、より広範な業務を自動化する「ハイパーオートメーション」。実現に向けた自動化の現状と課題とは。
RPAで小規模な自動化に成功した企業が、より広範な業務を自動化する「ハイパーオートメーション」を目指すケースがある。しかし思うようにプロジェクトを進められない企業も少なくないようだ。
日立ソリューションズの松本匡考氏(デジタルマーケティング営業本部 ビジネスクリエイション部 シニアエバンジェリスト)によると、ハイパーオートメーションはRPAとBPR(Business Process Re-engineering)、API統合によるシステム自動化(iPaaS)によって実現できるという。
ハイパーオートメーションを実現し、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するために必要なことは何か。松本氏とフジテックの友岡賢二氏(専務執行役員 デジタルイノベーション本部長)、オートメーション・エニウェア・ジャパンの由井希佳氏(カントリーマネージャー 日本営業統括)の3人が、2022年7月27日に開催された「自動化プラットフォームサミット」で対談した。
紙業務のための出社――コロナ禍でデジタル化の課題が顕在化
由井希佳氏(以下、由井氏): コロナ禍における自社のDX推進状況や課題について教えてください。
友岡賢二氏(以下、友岡氏): コロナ禍によってデジタル化の課題が顕在化しました。社内には紙を扱う業務が大量に存在し、テレワーク期間中にもかかわらず、部署によってはそうした業務に対応するために従業員がたびたび出社せざるを得ませんでした。紙業務をデジタル化するには大変な労力がかかりますが、DX推進のためには着手する必要があります。
松本匡考氏(以下、松本氏): コロナ禍は企業がIT活用を促進するきっかけになったと考えています。当社は「Microsoft Teams」を導入しているのですが、以前はほとんど使われていませんでした。しかしコロナ禍で頻繁にテキストコミュニケーションをするようになり、メールでは不便だということで、Teamsのチャット機能を利用するようになりました。
以前は「Salesforce」へのデータ入力もほとんど行われていませんでした。しかし、オンラインでの営業活動が増え、データの入力がないと案件の管理や運用ができなくなりました。そこで、Salesforceに入力されていない案件を評価しないことにしました。その結果、徐々にSalesforceへのデータ入力が定着したのです。
クラウドサービスをAPI連携させ、エンドツーエンドの自動化が主流に
由井氏: そうした状況で便利なのが、APIを使ってクラウドサービスと連携し、プロセスやデータがつながり合うIT環境の整備です。今後の戦略や、既に実施していることがあれば教えてください。
友岡氏: まず取り組むべきは、データ活用です。バラバラのデータを連携させ、ユースケースごとに整備し、最適な状態でタイムリーに引き出せなくてはなりません。プラットフォームにデータを集積し、APIを通じて自社システムとデータをやり取りできる環境が必要です。
フジテックでは、当社のエレベーターとエスカレーターを管理するために「Google マップ」を利用しています。大きな地震が発生すると、停止したエレベーターやエスカレーターがGoogle マップに赤で表示されます。復旧すると、赤から青に戻ります。緯度と経度を基に当社の基幹システムとGoogle マップをAPI連携することで実現しています。
松本氏: 米国では、APIを介して複数のクラウドサービスを連携させるiPaaS(Integration Platform as a Service)の利用が盛んです。新入社員の採用から入社に至るまでに必要な一連の手続きを自動化する例もあります。
日本では、オンプレミスの人事システムを利用しているケースも多いですが、APIを持たないオンプレミスの連携にはRPAを適用する方法があります。今日本はクラウドサービス普及の過渡期であり、社内に多く存在するAPI化されていないシステムをつなぐにはRPAが適しています。しかし将来的には、アメリカのようにAPIを利用したエンドツーエンドの自動化へシフトするべきだと考えています。
自動化プラットフォームで全てのシステムやデータを管理すべき
由井氏: iPaaSやRPAのようにプロセスをつなぎ、自動化を実現するためのツールはさまざまありますが、それらをプラットフォーム化にするにはどうすればよいでしょうか。
松本氏: 社内システムやクラウドサービスをただ個別に利用するのではなく、共通基盤を介して利用するのが理想です。
友岡氏: 私はAmazonの顧客体験が参考になると思います。今やAmazonのアプリがあれば、誰でも簡単に注文から配達までの処理を完了できます。Amazonは世界中のデータを基に顧客に最適な価格を提示できる仕組みを構築しているため、値引き交渉のような面倒なやりとりは必要ありません。Amazonのアプリは1つのインタフェースで全てのプロセスを顧客の要望通りに動かせます。自動化も同じように、顧客が望むリソースが常に準備されている状態にしておかなければなりません。
由井氏: 業務に必要なあらゆるシステムがつながり、いつでも利用できる状態になっていれば便利ですね。
松本氏: 複数のクラウドサービスを利用していると、個々のサービスの契約状況やIDとパスワードの管理にかなりの労力がかかります。こうした情報を1つの共通基盤で管理すれば、ユーザーは情報が集約されたポータルサイトを確認するだけで済みます。ポータルサイトにログインすると、自分の使いたい機能が確認できる。そうなれば非常に楽ですよね。
友岡氏: 複数のクラウドサービスを利用していると、データをバラバラに保管しがちです。しかし共通基盤があれば、データの一元管理が可能になりますね。
スキルを磨く意識が高まる「ジョブ型雇用」
由井氏: これからの5年、10年を見据えたアドバイスや、今後のあるべき姿についてお考えをお聞かせください。
松本氏: これからは「スキルを磨く」という意識が強まっていくでしょう。スキルを磨いた人たちが企業を強くします。そういった意味で、ジョブ型雇用は非常に重要な仕組みだと考えています。
当社はSIerとして、お客さまの要望通りにシステムを構築することで成長してきた会社ですが、それだけでは生き残れなくなるでしょう。お客さまの要望と世の中のあるべき姿には乖離(かいり)があります。そのあるべき姿に近づけるために、今後はメーカーと共にテクノロジーを磨き、ベストな選択肢を組み合わせてシステムを構築する必要があると考えています。
友岡氏: マンションに住んでいると、エントランスから入ってエレベーターに乗り、住んでいる階のボタンを押す必要があります。部屋に入る時も鍵を使ってドアを開けなくてはならない。あらゆる場面で、そうした面倒なことをなくしていけたらと考えています。自動化でもIoTやAI、RPAなどはあくまでも手段であり、最終的な目的は「あらゆるものを滑らかにつないでいくこと」だと考えています。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
関連記事
 RPA×iPaaSで“幻滅期”を脱する、日本企業のためのハイパーオートメーションの筋道
RPA×iPaaSで“幻滅期”を脱する、日本企業のためのハイパーオートメーションの筋道
RPAの限界を乗り越え、ハイパーオートメーションを実現するための鍵としてiPaaSが期待を集めている。RPAとiPaaSを“かしこく”活用することで、日本企業ならではのハイパーオートメーションを実現できるという。 iPaaSとは? 主要製品の棲み分けやメリット、運用のポイントを総整理
iPaaSとは? 主要製品の棲み分けやメリット、運用のポイントを総整理
SaaSの利用が増え、システム間の連携は従来と比べて複雑さを増している。そのなかで注目される、クラウドベースのシステム連携ツール「iPaaS」の特徴と、導入時のチェックポイントなどについて、Boomiの「Boomi AtomSphere Platform」を例に解説する。 iPaaS(Integration Platform as a Service)の利用状況(2021)/後編
iPaaS(Integration Platform as a Service)の利用状況(2021)/後編
RPAによる自動化の範囲を拡大し、一気通貫の業務自動化を目指す「ハイパーオートメーション」の文脈でiPaaS(Integration Platform as a Service)の有用性がうたわれている。一部の企業は早くもRPAを補完するツールとして認知しているようだが、「プロセス自動化の業」とも言える不安要素があるようだ。 iPaaS(Integration Platform as a Service)の利用状況(2021)/前編
iPaaS(Integration Platform as a Service)の利用状況(2021)/前編
近年、「iPaaS」(Integration Platform as a Service)という用語を頻繁に耳にするようになった。システム連携のコストや工数削減を実現するものとして、また業務自動化のあらたな一手として期待を集めているiPaaSの現在地をさぐる。 iPaaSとは? RPAとの違いや導入メリット、主要製品5つを紹介
iPaaSとは? RPAとの違いや導入メリット、主要製品5つを紹介
業務自動化における「RPAの弱点」を補い、処理を自動化する。サイロ化したシステムを連携して業務効率化を図る。