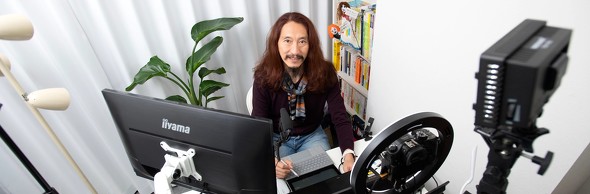澤円氏が語る「強制的デジタル化時代」の経営者のあるべき姿
コロナ禍によって世界の「リセットボタン」が押された。もはやインターネットが生まれる前の生活に戻れないのと同様に、われわれは「コロナ前」の生活に戻ることはできない。これを「一世一代のチャンス」と語る澤氏が、この先生き残るために何をするべきかを語った。
本記事は2020年12月22日のBUSINESS LAWYERS掲載記事をキーマンズネット編集部が一部編集の上、転載したものです。
サマリー
- コロナ禍はデジタル化への本気度合いを見る試金石
- 本気でDXを推進するならば、システム部門のトップを経営層に
- システム担当者に求められるのはファシリテーション能力
- システム部門が「もうそろそろ主役に」
コロナ禍によりデジタル活用が一段と推進されるようになり、デジタル化の実現度合いが企業活動の成否を大きく左右するという声も聞かれます。
そうしたなか「強制的にデジタル化を取り入れなければ、企業は本当に生き残れなくなる」と語るのは、元日本マイクロソフトの業務執行役員であり、現在は株式会社圓窓の代表取締役としてITコンサルティングや多数の講演を行う澤 円氏です。本稿では、デジタルトランスフォーメーション(DX)を取り巻く潮流や、デジタル化に取り組むうえで経営層、システム担当者それぞれが持つべき考え方について、澤氏に忌憚(きたん)のない見解を聞きました。
コロナ禍はデジタル化への本気度合いを見る試金石
――近年、「デジタルトランスフォーメーション(DX)」をキーワードとして、デジタル化推進の必要性が盛んに叫ばれ、コロナ禍の影響からその流れがさらに加速しています。企業の経営層は、事業活動におけるデジタル活用の必要性についてどのように見ていますか。
2020年1〜2月の時点では、企業イメージアップや採用促進などの理由から働き方改革やDXに取り組む経営者の方が多数派で、経営課題として真面目に取り組む方は少なかった印象があります。多くの経営者が、「会社をよくしたい」とは思っていながら、デジタルの活用方法がわかっていなかったことも理由にあるでしょう。テクノロジーに関わるバックグラウンドを持つ経営者の方はすごく少ないんですよね。さらに周りも経営者がITについて知らなくても困らない状態にしてしまっている。会議のときには、いまだに紙を配るわけです。経営者の方も「資料閲覧はタブレットだけにしなさい」という指示は出さないんですよ。
――経営者を含めてビジネスパーソンに今一番求められているのはどのようなことでしょうか。
「やめることを決める」ことです。やることを減らすためにもっとも大事なのは自動化であり、そこでITツールを使うことになるはずです。
日本は長時間労働を美徳とするところがあり、「システムではなく運用でカバー」しがちですが、僕はこれを「悪魔の言葉」「地獄への片道切符」と呼んでいます。運用でカバーする際には、誰かの時間を犠牲にしています。それを是とすることは経営の放棄とも言えるでしょう。国際競争力の低下や、優秀な人材の海外への流出にもつながりかねません。
こうした状況を改善するうえで、今は一世一代のチャンスです。新型コロナの影響で、インターネット元年である1995年以来のリセットボタンが押された状態だと言えるでしょう。
――四半世紀ぶりに訪れた大きな転換点というわけですね。
一般でもインターネットが使われるようになった1995年、「ファクスとメール、効率がよいのはどちらか」という特集が本当にありました。今聞くとギャグのようですが、当時はみんな本気だったのです。今はそれとそっくりの状態だと思います。リモートワークとFace to Faceはどちらが良いか、という議論はまさに同じ話でしょう。
新型コロナは今後ある程度は収束するかもしれませんが、変化したさまざまな運用は、コロナ禍以前には絶対に戻りません。かつてのような密な状態でレストランを営業するかといえばやらないのではないでしょうか。1995年の例で言えば、インターネットが普及する前に戻ることは考えられないですよね。
――それはたしかに考えられませんね。リモートワークを前提とした働き方は、急速に日本社会に広まっています。
リモートワークで価値が出せることを知った優秀な人材は、リアルな空間と時間を共有する仕事のやり方に疑問を持つわけです。経営課題として、デジタル化を推進できなければそうした優秀な人材をつなぎ止められなくなってきます。
コロナ禍でリセットボタンが押された今の状況は、強制的にデジタル化を取り入れなければ、企業は本当に生き残れなくなるでしょうし、企業の取り組みの本気度合いを見る最高の試金石だとも思います。
――企業ごとの意識の違いはすでに明確になってきているでしょうか。
例えばリモートワーク1つをとっても、本気で取り組んでいる企業とそうでない企業があるでしょう。その場しのぎで導入する企業は、いずれ出社勤務に戻すことを前提にしていますが、以前の状況に戻ることはありません。本音では元に戻ってほしいと考える経営層はすごく多いと思いますが、そうした感覚はアップデートしていくことがこれからの時代にマッチしています。
本気でDXを推進するならば、システム部門のトップを経営層に
――数年前から「攻めの情シス」という言葉も聞かれるなど、システム部門の活躍を推す声がありますが、ここまでのお話を踏まえると、デジタル活用の推進へ向け、システム部門にそうした働きを本当に期待している経営者もまだ少ないということでしょうか。
少ないでしょうね。多くの企業では日本型経営だといって、経営層になるまでにいろいろな部署を渡り歩かせたりしますが、システム部門のトップを経験させるケースはほとんど聞きません。しかし、DXを本気でやるのであれば、経営会議等に常にテクノロジーを理解している人が同席し、かつ予算を含めた権限を与えられていたほうがよいでしょう。
もちろん、システム部門の役職はエンジニアリングのバックグラウンドがないと務まりづらいという特殊性があるのは理解できます。ですが、それであればシステム部門のトップ自体を経営層に入れた方が、DX推進のスピードアップの確率が上がります。
システム部門長はITに関する業務だけを担当すれば良いという扱いを受けがちですが、本気でDXを推進する会社で、経営層にシステム部門のトップがいないなんておかしいんですよ。ましてやITの知識を持たないお飾りのCIOがシステム部門のトップを務めることなどは言語道断です。
――システム部門のトップが経営層に入っていくために、システム部門側からはどのように働きかけるべきでしょうか。
システム部門は仕事が多く大変だと思いますが、自社のビジネスに強く興味を持ち、プラスになる提案ができると良いでしょうね。
また、日本の産業構造の問題の1つとして、エンジニアリソースの8割程度がベンダーにいて、事業会社のシステム担当者が「発注屋」になってしまっていることがあります。発注屋が褒められる場面といえば、発注を安価で抑えられたときです。要するに、ITにかかる金額を費用としか見ていないことがこのような構図を生みます。DXを進めるうえでは「発注屋」としての視点を脱却し、ITコストを投資という概念で捉えられるようになる必要があるでしょう。
加えて、システム部門は社内で「エンジニアリソースが必要だ」「内製化したい」などともっと主張して良いと思います。エンジニアリソースを社内に持って内製する。そのトップは役員として存在する。こうした体制にしなければ、DXがうまくいくとは思えません。
――IT人材の登用にも関わるところで、今システム部門の担当者個人にはどういった能力が求められていますか。
特定の技術的なスキルよりも、感度が高くいろいろな物事に興味を持つこと。さらにそれが言語化できることだと思います。ここでいう言語化は、人に対して説明ができる言語化と、プログラミングによる言語化です。その双方をブリッジできる人材が、今一番求められているでしょう。
かつては調達や手配に手間がかかったサーバやネットワークなども今はクラウド化されています。クラウドを選択して問題ない際は即座にクラウドを利用し、空いたリソースを改善や実装にあてられるような考え方もIT人材として身につければ、タレントとしての価値は高まります。
――コミュニケーションとプログラミングの双方の能力が求められているのですね。
そうした能力を身につけるためには、アウトプットの機会をどんどん作って、いろんな反応を得ることが重要です。方法や内容は何でも構いません。アウトプットせずにインプットだけしていると、広く提供されている情報しか手に入りませんが、発信することでフィードバックが得られるなどさまざまな知見が集まり、インプットの質が上がります。また社外でのプレゼンスが高まれば、会社の価値向上にもつながります。周囲から一歩抜きんでるのであれば、とにかくアウトプットが重要です。
システム担当者に求められるのはファシリテーション能力
――DXやデジタル活用を進めるなかで、システム部門はどのような役割を果たしていくべきでしょうか。
重要なのはDXという言葉ではなく、会社の経営理念や組織として求める姿に対して、どこにデジタルが使えるか、どうやって自動化していくかと頭を使うことです。デジタル化は手段であって、何をもってDXと見なすかなどの議論は本質ではありません。ましてや、「システム部門がDXを進める」などとシステム部門を主語にするのは大間違いです。「システム部門も」です。
――システム部門に限らず、社内の各部門が経営理念を実現していく一環としてデジタル技術を活用していくのだと。
はい。例えば、開発を進めるうえでは、ユーザー部門やマーケティング部門等の現場の担当者が入って、企業の戦略としてプロジェクト化することが効果的です。
DXの流れのなかでシステム担当者に果たしてほしい役割は、会社をあげてのスクラムマスターになることでしょう。プロジェクトを推進するためのファシリテーション能力が必要です。決して、IT・テクノロジーの「説明員」ではないんですよね。
――これまでプロジェクトを推進するような役割を担ってきておらず、ファシリテーションが苦手だというシステム担当者の方は、どうすれば力を発揮していけるでしょうか。
その場合は通訳を見つければ良いでしょう。1人で全部やる必要はありません。自分が苦手なところを補完してくれる人がいるのが会社です。そうしたパートナーを見つけるのが大事でしょう。
もっと言えば、パートナーは社内でなくても構いません。社内で「言っていることがわからない」と思われると評価に直結するんじゃないか、などと不安な場合は、社外でメンターを見つけて壁打ちし、説明能力を高めていくのが良いと思います。
――プロジェクトを推進するうえでは、リソースや予算の確保も重要となるかと思います。社内で要望をあげたり交渉したりするうえでのポイントはありますか。
まず大事なことは、予算そのものに興味を持つこと。また、かかる値段だけを見るのではなく、生み出す価値を考えることが必要でしょう。「費用をかけることで、既存のコストがこれだけ下がる。またそこで空いたリソースを別の業務に割り当てることでより大きなビジネスができる」などということを、ロジカルに話せるようにしておくことです。
――事業部門など現場のニーズを吸い上げるうえではどのような取り組みが有効でしょうか。
システム部門の方へのコンサルティングの際によく言っていたのは、「営業の方にインタビューを依頼して、朝起きて夜帰るまでの間に何をしているかをヒアリングしてください」ということです。ヒアリングは、自分の観点から聞くのではなくあくまでヒアリング対象の人たちから見えている世界について、できる限り解像度高く聞くことが大切です。そうすると、例えば「一度出社して、メールチェックをしてから取引先に行くのではなくて、家から取引先へ直行するあいだに社外でメールが見られれば時間が短縮できるのではないか」など効率化のポイントに気づくことができるでしょう。
また経営の観点では、改善の取り組みを経営のリズムに組み込むことでしょうね。企業経営の成功を目的として、何をデジタル化すれば効果的かをいつも考えるのです。ここで絶対にやってはいけないのは、DXという仕事を足し算で増やすことです。
――業務のデジタル化を進めるうえで、シャドーITのように事業部門がITサービスを勝手に利用してしまうような事態に陥らないためには、システム部門として、どういった運用や働きかけを行えば良いでしょうか。
前職の日本マイクロソフトでは「べからず集をつくらない」というポリシーでIT管理を運用していました。これは日本マイクロソフトの社員のITリテラシーが高いからというわけではありません。日本マイクロソフトのポリシーは、セールスや法務、経理など、ITを専門としない社員を念頭に、ITリテラシーが低い前提でデザインされています。
それでも、高い自由度を設定しているのは、「べからず」と言われると、みんな身構えてしまったり、ルールが増えて覚えきれなくなったりしてしまうためです。また抜け道を探す人も出てくるでしょう。「自由度を高める。そのかわり、絶対に守ってもらうルールを少数定義する」というのがポイントです。決められた数少ないルールだけを厳密に守ることを徹底していました。
システム部門が「もうそろそろ主役に」
――経営課題の解決に向けたデジタルの活用が進んでいくなか、システム部門の方に向けたメッセージをいただけますか。
「もうそろそろ主役になろうよ!」と言いたいですね。システム部門の方へコンサルティングを行う際にも、「絶対に事例になって新聞に載るような仕事をしましょうよ!」と話しています。
――主役になれるぞ、と。
はい、企業戦略としてITが活用される時代がきているわけですから。もっと目立っていこうよ、と思います。
――本日はありがとうございました。
本記事は2020年12月22日のBUSINESS LAWYERS「システム部門が「そろそろ主役に」 - ITエバンジェリスト澤円氏に聞く、強制的デジタル化時代の歩き方」をキーマンズネット編集部が一部編集の上、転載したものです。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。
- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap
- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと
- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”
- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説
- 「偽人事部」からのメールに要注意 だまされやすいタイトルとは
- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術
- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap
- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは
- 情シスはなぜ忙殺される? 時間を奪う「計画外業務」の正体と対策
- ソフトバンクから8000人以上の情報漏えい、2026年版の10大脅威発表