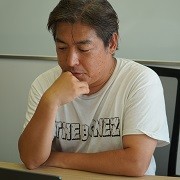今求められる「モダンな情シス」 全貌、変化する方法、アンチパターンを聞いた
情報システム部(情シス)の多くが、サーバのメンテナンス、ネットワークの保守といったインフラ関連の業務にリソースを充てている。“情シスのモダン化”を支援している梶原成親氏はそういった状況に警鐘を鳴らす。同氏が考える、今求められているIT部門とは。
多くの情報システム部(情シス)がサーバのメンテナンス、ネットワークの保守といったインフラ関連の業務にリソースを充てている。コストの最適化、削減が目的とされることも多く、企業のビジネス力向上には直接寄与しないこともある。
そういった状況に警鐘を鳴らすのが、“情シスのモダン化”を支援している梶原成親氏だ。同氏は「本業の課題をソフトウェアで解決してビジネス力を向上させる『モダンな情シス』が求められている」と語る。
モダンな情シスとはいったどういった考えなのか。梶原氏への取材から、モダンな情シスの全貌や、変化する方法、アンチパターンが分かる。
モダンな情シスはどのように生まれた
――最初に、梶原さまの経歴や、IT部門の業務で重視していること、現在の役割を教えてください。
梶原氏: 以前は楽天の情報システム部に所属し、開発者向けの生産性向上ツールの提供や、全社向け情報システムの統括していました。
もともと生産性向上に関わる部署と情報システムに関わる部署は分かれており、同じ部署になったときは生産性向上よりもセキュリティが重視されがちでした。また、情報システムは当たり前に動作することが期待され、トラブルが発生すると社内から批判されるストレスもありました。しかし、情報システムの役割は、セキュリティを重視して安定運用できるツールを導入することだけではありません。従業員の無駄な業務を減らし、企業の業績向上に貢献することを重視してチームをリードしました。
同じ企業でも部署や役割の違いから対立が生じることがあります。現在は顧問としてさまざまな企業に関わり、そのような問題の解決に取り組んでいます。
また、楽天に所属した後はマッチングアプリ「Pairs」を提供するエウレカ、CXプラットフォームを提供するプレイドなど複数企業のIT部門を担い、現在は年10泊から購入できるハイエンドな別荘を展開するNOT A HOTELのCorporte IT(部門)を統括しています。
――企業さまの支援とIT部門の業務の両方をされているのですね。モダンな情シスという考えを持つようになったきっかけを教えてください。
梶原氏: 私が仕事を始めた2000年ごろはオンプレミスが主流で、「Microsoft Exchange Server」でメールの送受信を管理し、Microsoftの「Active Directory」でセキュリティの設定やファイルサーバの権限管理をしていました。IT部門の主な仕事はサーバやネットワークなどのインフラの管理でした。
しかし現在、状況は変わってきています。「Google Workspace」や「Microsoft 365」などのSaaSが普及し、サーバのメンテナンスよりもサービスの運用や管理が業務の中心となりました。かつてオンプレミスで提供されていたものは、ほとんどがSaaSとして提供されています。
オンプレミスの運用で必要な監視の体制や工数を減らし、空いた工数は本業の効率化や、DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進に充てるなど、本業の課題をソフトウェアで解決することに注力したほうがよいと考えました。
――SaaS、クラウドサービスの活用が重要なことが分かりました。では日本企業のSaaSの活用状況を教えてください。
BetterCloudの調査「The 2021 State of SaaSOps Report」によると、米国でSaaSの活用が進んでいる企業は、1社当たり約212のSaaSを導入しています。SaaSをベースに業務するのが米国では当たり前になりつつあります。
SaaSの活用が進んでいると言われる国内IT企業でもSaaSの導入は70ほどです。調査の定義によると70はまだトランジションの途中で米国に比べて10年遅れています。モダンなIT環境を整えるには、全ての業務で提供されているSaaSを熟知することが重要です。
モダンな情シスを構成する3つの要素
――日本企業ではまだSaaSの活用が進んでいないのですね。それでは本題の「モダンな情シス」について教えてください。
梶原氏: モダンな情シスを構成する3つの重要な要素があります。1つ目は、「SaaSのベストプラクティスを探求する」ことです。SaaSにはさまざまな機能があるため、従業員の業務をSaaSで「どのように効率化できるか」「生産性を向上させるか」という引き出しを増やすことが求められます。
2つ目は、SaaS、クラウドサービスが前提となるため「クラウドサービス上の重要データを守れる」ことです。
クラウドサービスに重要な企業データを保存するため、その管理や運用は非常に重要です。例えば、Googleはユーザーベースまたはデバイスベースの認証「BeyondCorp」や、ゼロトラストセキュリティの概念に基づいた各種ソリューションを提供しています。
これらのセキュリティポリシーを守るためには、SaaSに保存したデータを保護する運用設計をできる人が必要です。そして、そういったセキュリティポリシーを設計できるということが、モダンな情シスの重要な要素です。
3つ目は「IT部門が門番のようにならない」ことです。何かあるたびにIT部門が介在してストップをかけるのではなく、全社の業務のアジリティーを高めるための役割を果たすべきです。IT部門は社内のコンサルタントとして問題解決に取り組むことが重要です。
業務している人の多くは、ITで業務を改善する方法を知りません。そうした人たちをサポートし、SaaSや他のテクノロジーを使って問題を解決することが求められます。
――SaaSを運用する具体例をお願いします。
梶原氏: 簡単な例としてファイル共有のケースを考えてみます。例えば、「Google ドライブ」でファイル共有する際、相手がGoogleアカウントを持っていない場合でも、URLを知っていればファイルを共有できるようにするとします。
これを全ての部門で適用してしまうと情報漏えいのリスクが高まります。そこで、例えばIT部門が管轄する特定の部門に対してのみ共有を許可し、申請を受けてから公開するようにすることで、リスクをコントロールして適切にファイルを共有できるようにします。
次にベストプラクティスの考え方についてです。「Salesforce」の設定ミスによる情報漏えいが頻繁に起きています。Salesforceのデフォルト設定が変更されたにもかかわらず、その変化に気づかず使用してしまったために情報漏えいが起きました。SaaSは常に機能を更新し続けるため、その変更をウォッチし、ベストプラクティスを常に探求する必要があります。
これはあくまで非常に簡単な例です。IT部門がベストプラクティスを追求し続けてリスク管理を徹底することで、適切な情報共有とセキュリティ対策が可能になると考えます。
――SaaSの導入に慣れていない企業がSaaSを導入する際、情報漏えいを避けるためにまずやるべきことを教えてください。
梶原氏: 最初に、導入するSaaSの機能を熟知する必要があります。管理コンソールや管理画面などの設定を一つ一つ把握しなければなりません。
デフォルト設定のままで予期しない事態が起きることを避けるため、全ての設定を確認し、自社にとって最適な形に設計することが重要です。よく「SaaSを導入するならセキュリティをしっかり理解していないといけない」と言われますがその通りです。IT部門は設計力と検討力が試されます。
利用ポリシーを策定して企業全体を動かす力も必要になるので、SaaSの導入は決して簡単ではありません。
――オンプレミスが中心でSaaSに慣れていない人が多く、採用されづらい企業はどうするのがよいでしょうか。
梶原氏: 外部の専門家を呼び、経営層に「SaaSをどのように活用すれば業務が改善されるか」を示すのはテクニックの一つです。
経営層が見ているのはシステムではなく業務の変化です。本業がどのように改善されるのかという観点で成功事例を示すことは、導入を容易にします。
門番化したIT部門がマインドチェンジするヒント
――モダンな情シスの概要や、SaaS導入の基本がよく分かりました。ただ、SaaSの便利さが分かっていても、なかなか最初の一歩が難しい方もいると思います。
梶原氏: そうですね、成功体験がないと難しいですね。IT部門の人たちは失敗すると社内から突き上げを受けることが多いため、変化を恐れて保守的になりがちです。
ただ、IT部門のメンバーも企業の一員なので、企業の成長のために何をできるか考えることが重要です。IT部門だからこそ、運用のルールやフローが非効率と感じられます。それを自分たちの知識やテクノロジーで解決すると称賛や感謝が集まり、そのような成功体験を積み重ねることで人は変われると思います。
また、IT部門は経営者とあまり会話ができていないことが多いと思います。経営者と会話した際に「こういうことができる」と提案すると、経営者はきっと「ぜひやってほしい」と言うでしょう。経営者は高い費用を払って外部コンサルタントを雇うより、社内の技術者に「ぜひやってもらいたい」と思うでしょう。
IT部門は周囲と関わらないと自分たちへの期待が分からないので、外からの話を聞いみるのがよいです。
――梶原さまの印象に残っている成功体験を教えてください。
梶原氏: そうですね。営業事務の方が販売フローを全て「Microsoft Excel」で管理していました。ある時、その営業事務の方が急に入院されて業務が滞ってしまいました。別の方がその仕事を引き継ぎましたが、長時間残業をする状況になってしまいました。そこで、まずはその方の話を聞くところから始めました。
話を聞いて作業内容を見ると多くのコピペ作業がありました。例えば、あるシステムからデータをコピーしてスプレッドシートに貼り付け、それを印刷してメールで送るといった具合です。ITエンジニアの視点から見ると、システム間のデータをAPIで直接やり取りする方が効率的ですが、現場の方はそのようなテクノロジーに疎いため、手作業で実施していたのです。
そこでローコード開発をできるiPaaSの「Zapier」を使って、自分でメンテナンスできるように支援しました。導入するだけではなくメンテナンスの方法も教えることで、情報システム部門に負担をかけることなく現場で運用できるようにしました。「魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教える」わけです。
週に複数回、1時間のペアワークを2カ月間続けました。その結果、例えば受注が来たら「Slack」に通知され、ボタンを押すとクラウドサインが送られるなど、多くの作業が自動化されました。これによって人件費が削減され、ミスが減り、営業部門の方々も進捗(しんちょく)状況を把握しやすくなり、感謝されることも増えました。
――IT部門への周囲からの期待が分かっているからこそ、困っている方の存在に気付けたわけですね。難しい質問になりますが、そもそもIT部門への期待が分かっていない方はどうしたらよいでしょう?
梶原氏: それは経営の問題でもあると思います。経営層は各部門にどのように期待しているのか伝えることが重要だと思います。その際、コスト削減などのネガティブな側面だけでなく、本業を前に進めるためにどのような期待があるのか、といったポジティブな側面を伝えることが大切です。
また、IT部門の方も自分のスキルセットや貢献できる方法を考えることが大事です。そして、期待されていることを見える化することも重要です。そうすることで、自分がどのように具体的に貢献できるのかを見つけやすくなります。
社内の人が「IT部門は話しかけづらい」「コラボレーションしづらい雰囲気がある」と考えている場合は、窓口を開くのも一つです。私がよくやるのは、週に1回「何でも質問できる時間」を作ることです。興味がある人がその時間に「Googleカレンダー」で「Google Meet」に参加してくるといった形ですね。
――特定の時間を設けるといった、習慣付けからはじめることが大事かもしれませんね。
そうですね。ゴールが見えている場合はそこから逆算して計画を立てることが重要です。しかし、最初からゴールが見えない場合は、まずできることを試してみましょう。その中から、良さそうな方向性を見つけて進んでいくことが大切です。
Slackなどを使っている場合は、まず「問い合わせ用のチャンネル」や「相談用のチャンネル」を作りましょう。先ほどのZapierの例ですが、導入する際はZapierの使い方をお互いに教え合うためのチャンネルを作りました。そこでは、Zapierで作ったものを投稿してみんなで共有し、学び合っていました。
対面以外のコミュニケーション手段が増えている今、さまざまなチャンネルを使って情報提供することが重要です。何が役立つかは人それぞれ異なるので、情報提供の場を増やすことは大切ですね。
私のチームは週に1回、便利な機能やツールを社内ブログで紹介しています。最近は、Google Workspaceを使っている人に向けて「予定確認ページ」ができたことを紹介しました。新機能に触れる機会が少ない人に向けて情報共有することは有益な取り組みだと思います。
モダンな情シスに変化する際のアンチパターン
――IT部門がマインドチェンジする方法が分かりました。では、モダンな情シスに変化する際のアンチパターンを教えてください。
梶原氏: 一気に大きな変更をするのではなく、まずは小さな実験をして、その結果を基に少しずつ改善を繰り返す方がよいです。
例えばSaaSを全社に一斉導入するのではなく、一部門で試してみて効果を評価し、振り返りを実施します。その際、導入後アンケートを実施して、実際に使用した人たちの声を聞き、フィードバックを基に取り組みを広げていくことが重要です。
そしてその活動を可視化し、どのような良い成果があるのかを明確に示すことが重要です。上司に正しく伝えないと自分の努力が理解されない場合もあるので、伝え方にも気を配りましょう。
基本的に新たな提案に反対する人は少ないと思います。ただ、納期や工数など、既存の仕事に影響を与えないかどうかは検討すべきですね。そういった調整は、行動して失敗する前に上司に相談したほうがいいと思います。
――反対勢力が存在する場合、どう行動するのがよいでしょう。
梶原氏: やはり物事が変わることに対して抵抗がある人は一定存在します。「今の業務がどうなるのか」「一時的に負荷が高まるのが嫌だ」といったことを言われるでしょう。そういう方には「新たな仕組みに慣れると工数は少なくなる」といった見通しを正しく説明することが重要です。
変化に対するネガティブフィードバックは必ず起こるので、そういう時に困らないようにしておく必要があります。変化を恐れる人が何に抵抗を持っているのかを常にウォッチしておきましょう。
――業務でお悩みのIT部門の方へ向けたメッセージをお願いします。
梶原氏: SaaSをうまく使うことはそれほど難易度が高くないと思います。そして、SaaSを使うことでさまざまな現場の人たちから感謝されることが多いと感じています。
私のモチベーションは業務を楽にしたり効率化したりして、それを喜んでくれる人が存在することです。そういったことに価値を見出す人は、ぜひSaaSを活用して現場を改善・改革することに挑戦してみてください。
※2024年5月30日12時10分、「現在はホテルとして貸出可能な住宅を提供しているNOT A HOTEL」を「現在は年10泊から購入できるハイエンドな別荘を展開するNOT A HOTEL」に修正しました。
関連記事
 トヨタの情シスはDXにどう取り組んでいる? 事例に学ぶ「成功するDXの進め方」
トヨタの情シスはDXにどう取り組んでいる? 事例に学ぶ「成功するDXの進め方」
トヨタの情シスはDXにどう取り組んでいるか――。NECの自社事例やITRのDXに関する調査結果と合わせてチェックすることで、日本企業のDXの現在地が見えてくる。 コロナ禍3年間の「情シス悲喜こもごも」 SNSで人気の情シスたちが語る
コロナ禍3年間の「情シス悲喜こもごも」 SNSで人気の情シスたちが語る
コロナ禍、企業の情シスはどのような課題に直面し、どう解決したのか。そしてアフターコロナの課題は何なのか。SNSで人気の情シスがこの3年間を振り返った。 「Microsoft 365」運用のNG集 情シスから寄せられた困った、焦った事案
「Microsoft 365」運用のNG集 情シスから寄せられた困った、焦った事案
Teamsのチャネル管理やOneDriveのファイル共有状況など、Microsoft 365では多くのアプリを使えるが故に、情シスが把握すべき範囲も広い。管理が不十分だと、時に情シスが思わず焦る事故が起こる恐れもある。 なぜ情シスは評価されにくいのか? 間違った評価制度と年収アップのコツ
なぜ情シスは評価されにくいのか? 間違った評価制度と年収アップのコツ
かつて情シスは「一番PCに詳しい人」が任命されがちでした。評価や昇給の成功事例は少なく、転職以外で昇給に伸び悩むケースをよく見ます。情シス部長を2社で担当し、エンジニアの評価制度コンサルティングを実施する筆者の経験から、情シスの評価制度の作り方や年収アップ交渉のコツをお話します。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。
- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap
- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”
- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと
- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説
- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術
- 正規認証が悪用される? Microsoft 365の権限を奪う「デバイスコードフィッシング」とは
- 極悪なウソつきはGeminiかGPTか? 4つのAIモデルをガチ対戦させてみた結果:865th Lap
- ソフトバンクから8000人以上の情報漏えい、2026年版の10大脅威発表
- 「2026年は脱MySQLすべき」エンジニアたちが突然騒ぎ出したワケ:864th Lap
- ランサムウェア対策、何から始める? 悩める中小企業を救うIPAの"神ツール"
 梶原成親氏
梶原成親氏