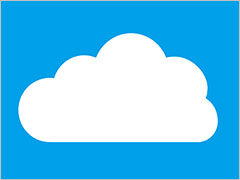「バックアップソフト」とは 導入の目的、メリットを解説
「バックアップソフト」に関する最新情報を紹介します。IT担当者やITを活用したいビジネス/バックオフィス部門の担当者に、役立つ製品・サービス情報や導入事例、業界動向を集めました。
バックアップソフトとは
バックアップソフトとは、コンピュータやサーバのデータや設定情報を別の場所にコピーして保存するためのソフトです。バックアップ元のシステム障害などが発生し不具合が生じても、バックアップを元に復元することができます(続きはページの末尾へ)。
バックアップの基本
フルバックアップと増分バックアップ
バックアップツールはまず始めに、対象とするシステムのフルバックアップを取る。ここで用いられているのがイメージバックアップという手法で、ファイル単位ではなく、OSやアプリケーションまでを含むディスクイメージ全体を保管するものだ。
これによって仮に元のHDDが壊れてしまった場合でも、新しいHDDを用意して、そこにイメージファイルを戻すことで、簡単かつ迅速にリカバリーを行うことができる。OSやアプリケーションの再インストールといった手間も不要だ。専任のIT担当者を置くことが難しい企業にとっては、非常に有効な手段だといえる。
こうして最初にフルバックアップを取ってしまえば、2回目以降のバックアップは、前回のバックアップから増えたデータ分だけを保存していけばいい。これが増分バックアップだ。毎回フルバックアップする必要がないので、バックアップ時間の大幅な短縮を図ることが可能となる。
ちなみに多くの企業が最初にフルバックアップを取り、以降は定期的に増分バックアップを取得、一定期間ごとにフルバックアップを取り直す、という運用を行っているケースがほとんどだろう。フルバックアップ取得時には比較的長いシステム停止が必要な場合もある。
一部のバックアップツールでは、増分データの世代管理を行い、指定回数の増分バックアップを取得すると、最も古い世代の増分データをフルバックアップデータに「合成」して、新しいフルバックアップデータを自動で作成するという機能を持つものもある。
例えば、ArcserveUDPでは、最大で1440世代まで設定することができるので、計算上は4年弱の間、毎日の増分バックアップだけで運用を回していくことができるという。フルバックアップ部分のデータは重複排除され、さらに圧縮されて保管されるので、データ保管用のディスク容量も大幅に節約することができる。ITコストの削減にもつながる機能だ。
仮想環境をエージェントレスで自動バックアップする
バックアップデータを格納するための復旧ポイントサーバ(Recovery Point Server:RPS)を立て、ここにコンソールを接続して各種設定を行い、物理/仮想マシンのデータをRPSにバックアップする。
このとき、物理マシンには増分データを把握するために、バックアップツールのエージェントをインストールする必要があるが、実は仮想マシンにはエージェントが不要で、「VMware ESXi」や「Microsoft Hyper-V」などの仮想マシンを管理するオーケストレーションツール(VMware vSphere、System Center)側で変更ブロックを把握し、その情報をバックアップツール側にフィードバックしてくれるのだ。具体的には、バックアップツールが仮想化ソフトウェアのAPIを介して、仮想化ソフトウェア上で稼働している全ての仮想マシンのバックアップデータを一括で取得する。
通常、人間1人が面倒を見ることができる物理サーバの台数はせいぜい数十台だが、仮想マシンは簡単に増やしていくことができる。数百台、多いところでは数千、数万台の仮想サーバを構築している企業もあり、こうした規模の仮想マシン全てを個々にバックアップすることは非常に大変だ。
その際に仮想化ソフトウェア側の機能ではあるが、仮想化ソフトウェア1つを対象にすれば、その上で稼働している全ての仮想マシンを一括でバックアップできるというエージェントレスの仕組みは、ユーザー企業にとって非常にうれしい機能だといえる。
テープバックアップとは
バックアップに用いられる磁気テープとは
1950年代に巨大なオープンリール型の商用データ記録磁気テープが登場したのを皮切りに、多くの企業においてシステムバックアップに利用されてきた磁気テープ。テープの上のフィルムに塗布された粉末状の磁性体を磁化し、さまざまな情報を記録する仕組みだ。つまり、「0」と「1」の配列で記録されるデジタル情報と同じように、磁性体をS極とN極に磁化し、S極とN極の配列によってテープにデータを記録するもので、この磁気テープが納められたカートリッジをドライブやオートローダーといった装置に挿入し、情報を記録する。
企業がバックアップ用途に使ってきた磁気テープは、2000年代には多くの規格が市場に展開されていたことは、ご存じの方も多いだろう。エントリークラスでは、DDS(デジタルデータストレージ)/DAT(デジタルオーディオテープ)やDLT(デジタルリニアテープ)と呼ばれるものから、ミッドレンジにはAIT(アドバンスドインテリジェントテープ)やLTO(リニアテープオープン)、そしてエンタープライズクラスにはIBMやOracleなどがシステムとして提供しているTSファミリーやTシリーズといったベンダー固有の磁気テープカートリッジが存在する。
しかし現在は、ミッドレンジを中心にエントリー領域でも利用されているLTOが中心的なオープンフォーマットの規格であり、「IBM 3592」TSシリーズやOracleのT10000シリーズといったハイエンドモデルの一部はいまだに残っているものの、バックアップに用いられる磁気テープの規格はLTOがスタンダードといっても過言ではない。
なお、記録密度を高めていくためには磁性体の微粒子化を進めることが必要だが、従来利用されてきたMP(Metal Particle)磁性体でその限界を迎えたことから、今ではBaFe(Barium Ferrite:バリウム・フェライト)磁性体が主に利用されている。提供ベンダーの違いによる互換性を確保する意味でも、LTOの規格ではBaFe磁性体を利用することが明記されている状況だ。
磁気テープを用いたバックアップの重要性
磁気テープを用いたバックアップは、すでに何十年もの歴史があるが、磁気テープ自体の存在を知らない世代が増えている。そもそもCDやDVDが登場する以前は、3.81mm幅のテープを用いて音楽を録音するカセットテープが一般家庭にも広がり、多くの人が“磁気テープで情報を記録する”ということになじみがあったはずだ。
しかし、今ではCDやDVDはもとより、デジタルデータによる音源配信などを利用して音楽を楽しむことが増え、磁気テープそのものを目にする機会が少なくなったのが実態だろう。そのため、データ保護の仕組みとして磁気テープという選択肢があることを知らない方もいるのが現実だ。
バックアップにおける基本となる「3-2-1ルール」
その意味でも、テープバックアップはもはや古いテクノロジーと思われがちだが、現実的には企業におけるデータ保護の手法として重要な位置付けであることは間違いない。それは、データ保護のためのバックアップ運用の基本的な考え方となっている「3-2-1ルール」が関係してくる。
この考え方は、米国国土安全保障省(DHS:United States Department of Homeland Security)のサイバーセキュリティー・インフラストラクチャー・セキュリティー庁(CISA:Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)によって提示されたもので、重要なデータ保護にはファイルのコピーを3つ(うちバックアップは2つ)保管し、データを保管する記録メディアは異なる2種類を用意、そしてコピーのうちの1つはオフサイトもしくはオフラインに保管するというものだ。
データを保管する記録メディアには、ディスクやメモリはもちろん、オンラインストレージなどのクラウド環境、そして磁気テープがその候補に挙がってくる。最適なバックアップ環境の構築や運用におけるノウハウはインテグレーターなどがコンサルティングを含めて最適化支援を行っているが、その中で磁気テープによるテープバックアップは現在でも重要な選択肢の一つだ。データ保護におけるポリシー策定を自社で行う際には、この3-2-1の法則をベースにバックアップ運用を考えることが重要だ。
製品カタログや技術資料、導入事例など、IT導入の課題解決に役立つ資料を簡単に入手できます。
- リチウムイオン電池も終了か 40年眠っていた、充電を爆速化する「古くて新しい電池」って?:866th Lap
- 「データ分析をAIに丸投げ」はまだ早い? 現場が答えた賢いAIサービスの使い分け
- AIに書かせたコードはどこが「危ない」? プロがガチ採点して分かったこと
- 「国家資格で食える」はもう古い? 5年分の調査で見る、AWS、セキュリティに続く“次の資格”
- PC高騰、いつまで続く? IDCアナリストに聞く値上げ時代の賢いPC調達術
- Notion導入で生成AI活用のナレッジ基盤を構築 従業員の情報意識にも変化
- ラックの基本とデータセンター選び、5つの視点
- 「ChatGPT」が開発で役に立たない納得の理由 ただし、GPT-3.5版に限る:787th Lap
- コーディング中に突然「Gemini」が暴走、これはバグか、それとも……?:843rd Lap
- AIアプリ開発「Dify」って結局何がすごいの? 機能、料金、ユースケースを徹底解説